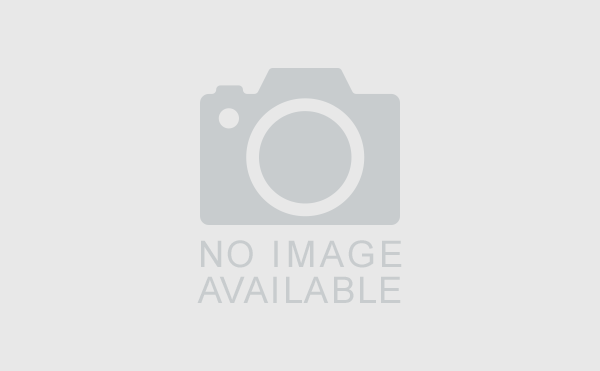「税という社会の仕組み」諸富徹
サブタイトルは『納税は義務権利です』。税制の成り立ちや国の制度など見方によっては権利とも考えられるという筆者の見解。本書を通読し、考え方としてわからなくもないが、やはり納税の義務感はぬぐい切れない。納税を権利として納得できるかは別として、本書は各種の税・社会保険料の成り立ちなどの解説と各種の税と社会保険料のバランスなどが分かりやすく説明されている。思想の偏りもないように感じた。
税を権利だと考えるのは以下の4点を踏まえてのものとのこと。
1.国民には国家に仕事をしてもらう権利(させる権利?)がある
2.国民は自分たちの同意なしに課税されない権利を持っている
3.国家が国民の意に沿わない方向に向かうのであれば国家を取り換える権利がある(革命権)
4.国家が上記3つを守っている限りにおいて、税はその対価として支払うもの
仕組みとしては理解できるが、「税が権利」という表現はピンときませんでした。
他国も含め税の歴史を見ると、「一時的」「臨時」で始まった税目が恒常的なものになっていく、という事実は興味深かった。時代とともに新たな歳出が出てくるのであろうから、一度始まった税目を廃止するのは難しいだろう。だからと言って、ガソリンの暫定税率の継続をしょうがないものと思う気にはなれないが。。
所得が多くなればなるほど税負担率が減る、というのは聞いたことがあったが、具体的にどういうことかの説明があった。単に所得が高い人ほど配当所得の割合が多く、割合の多い部分の税率が20%であるという単純なことであった。国民民主党の金融所得の税率を金融所得に応じたものに見直すという案は納得がいくものだった」。
本書の中でも税制調査会のインナーが税制を決定していることについて触れられていた。ただなぜインナーが強いのかについての言及はなかった。なぜ財務省やインナーに対して政治家は弱いのか、なぜ財務省のOBが税制調査会の中心メンバーなのか、には疑問が残る。
法人税が下がり続けている実態について、長らく疑問に思っていたが、本書を見て納得したわけではないが、経緯は理解した。本書では法人税率が高いと資本が海外流出する旨の説明であった。ただ資本流出(や海外への所得移転)の難易度はわからないが、実際に大量の資本流出が発生してから考えてもよいのではないかと感じた。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4396d574.3690ca45.4396d575.d862e05f/?me_id=1213310&item_id=21233042&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4844%2F9784480684844_1_392.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)