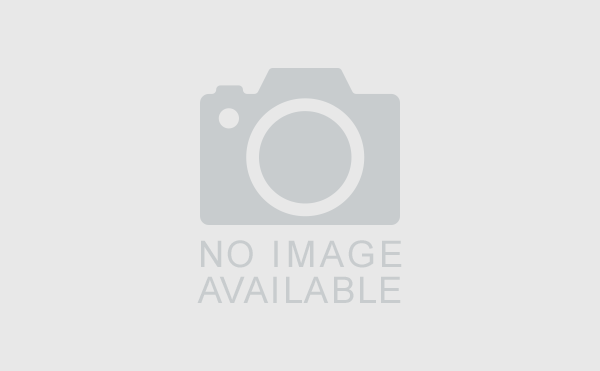「学者が見落としたお金の仕組み」児保祐介
「国債残高は減らさなければならない」、「税は国家予算の財源」とマスコミ、財務省や多くの政治家が述べているが、これらの考えが誤りであることを、貨幣の定義、信用創造、内国為替、日銀と国債、国債と通貨量、税の機能などを通じて指摘している。政府や財務省の施策は経済の停滞・縮小、格差拡大を助長する誤ったものであったことがよくわかる国民必見の一冊。
「国債残高は減らさなければならない」と言われることがあるが、国債残高が減少していきゼロになった場合を考えると、「通貨量の減少→消費の抑制→所得減」となることが示されている。仮想的な国内各主体の数値をデフォルメしたバランスシートを用い説明されており、イメージは十分つかめる。また、複式簿記の性質上当然に「誰かの借金は、誰かの資産」であるが、「政府の負債(国債)が、国民(と日銀)の資産」とも言われている理由がよくわかる。
金融機関は、お客さまからお預かりした預金を、融資の原資にしていると新入社員の時の習った気がするが、100%正しいとは言えないことに気付かされた。銀行は融資の実行と同時に預金を創造するからである。またこれが真の信用創造であり、「お預かりした預金の90%を融資の原資にし、またその融資から創造された預金の90%が融資に、、、」という一般的な信用創造の説明は明らかに誤りであることに気付かされた。
「スペンディングファースト」という言葉を初めて知った。これは、「ある年度において、その年度の予算は決まっているものの、実際の税収が発生する前に支出は発生する。この支出は国債で賄われている。」という意味。つまりは、税収以上の支出があってもその時点においては問題がない、税金は政府が使うお金の財源ではない、とうことだ。
「通貨量が増加すると当該通貨の信用がなくなる、ひいてはインフレが起きる。」と言われることがあるが、「通貨量が増加し、インフレが起きてもそれに伴い当該化通貨による納税額が増加する(=当該通貨の需要が増加する=当該通貨の信用はなくならない)」という説明がされており、納得感もある。「通貨量の増大が即通貨の信用、信認がなくなるという考え方は短絡的」という指摘であった。
「国債の発行過多は債務不履行のリスクがある」と言われることがあるが、自国通貨建ての国債であれば、日銀の買取/借り換えがあり、債務不履行にはならない。外貨建ての負債であれば、当該外貨を稼いで返済しなければならない、つまり自国の製品やサービスの需要がなければ外貨は稼げないため、債務不履行は生じうる、という説明である。ただし、1997年のロシアのデフォルトのように、固定相場制を採用している場合、ユーロのような共通通貨建国債の場合または地方債の場合は異なる、という例外もしっかり説明されている。
税は国家予算の財源ではないのであれば、税金はなくてもいいのではないか、と思ってしまうが、そうではないことまで解説されている。「税の(5つの)機能」として説明されている。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4396d574.3690ca45.4396d575.d862e05f/?me_id=1213310&item_id=20771834&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9731%2F9784434309731_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)